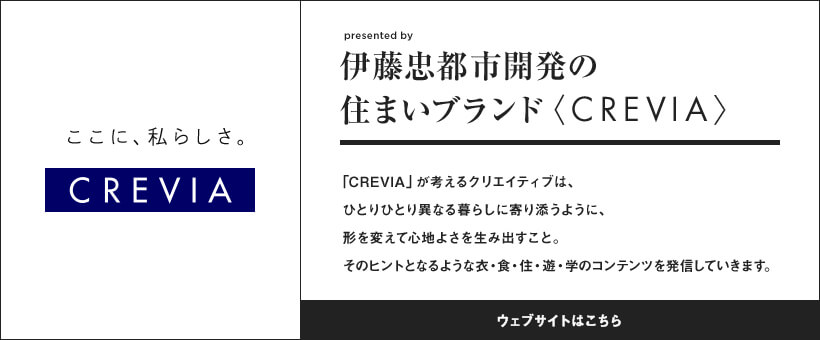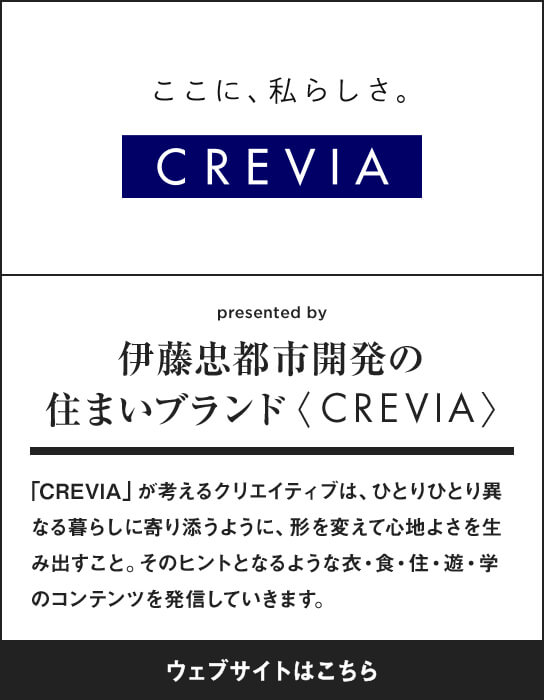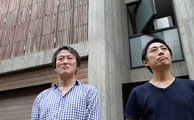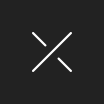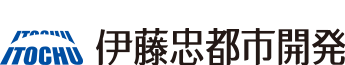深く、美しく、凛として――。京都・壬生にある染屋「京都紋付」は、1915年の創業以来、100年以上にわたり“黒一色”に向き合ってきた。和装文化の象徴である黒紋付に始まり、いまでは洋服やアップサイクルへと、その技術と美意識は時代とともにしなやかに進化している。
もう着られないと思っていた服に、深い黒をまとわせることで新たな命を吹き込む「リウェア」という選択。それは、ただ再生するのではなく、記憶を継ぎ、未来へとつなぐ営みだ。伝統を守るとは何か。継承とはどうあるべきか。その答えを聞きに、革新を続ける4代目・荒川徹氏のもとを訪ねた。


1958年 生まれ。(株)京都紋付、(有)キョウモン代表取締役 社長。大学卒業後、電気機器メーカーに入社。退社後、1983年に京都紋付入社。 染色加工業の他、KUROZOMEデニムの販売、着物メンテナンス事業などを手掛ける。テキスタイルアップ サイクルプラットホーム理事。

-


京都・壬生に工房を構える「京都紋付」は、1915年の創業以来、100年以上にわたり“黒一色”にこだわり続けてきた染め屋だ。かつては礼装の黒紋付きを主に手がけ、日本の伝統文化を支える職人たちの技術と誇りが受け継がれてきた。黒さを競う黒紋付の世界で、先代から脈々と追求してきたのは「絶対的な黒」だ。

4代目の荒川徹氏はいう。
「着物の中でも、とりわけ格式が高いのが黒紋付五つ紋です。模様のない無地の着物だからこそ、黒の深さがその価値を決定づけると言われています。そのため、黒の美しさを極めることは、まさに職人の矜持でもありました」

そうした黒への誠実な探求は高く評価され、昭和天皇の大嘗祭においては装束「小忌衣」の再現製作を任されるという栄誉を受けた。
「黒という色には、谷崎潤一郎の著書『陰翳礼讃』にも書かれているように、日本人が古くから育んできた陰影の美意識が宿っているのです」
実際、日本には「墨色」「漆黒」「濡羽色」「玄」「鈍色」など、黒を表す言葉が数多く存在する。それは、黒が無限のニュアンスと意味を持つ特別な色であることを物語る。障子越しに差し込むやわらかな光や、行灯のほのかな明かりを愛でてきた日本人だからこそ、黒の陰影にえも言われぬ美しさを見出してきた。
-


しかし、伝統的な黒紋付の市場は時代とともに縮小し、最盛期には300万反あった生産量も、現在は2000反以下に。組合の事業所数も100を超えていた時代から、わずか3社にまで減少して組合は解散してしまった。かつて武士の礼装として始まり、大正初頭には宮中参内の喪服として定められ、現代においては冠婚葬祭に用いられている黒紋付だが、時代が移り変わる中で、その文化を守り継ぐことは容易ではない。
「黒紋付は、歌舞伎などの伝統芸能の世界で欠かすことができません。つまり、日本の伝統文化を守るためにも、黒染めの技術を守り、次世代に繋げる責任が私たちにはあるのです」
そう語る荒川氏は、時代の流れに抗う代わりに、伝統の核心を守りながら、その技術を新たなフィールドへと展開していくことを決意。その一つが、洋装の黒染めだった。今から約30年も前のことだ。
染めることが非常に難しいとされる絹を用いた黒紋付の製作で、長年にわたり高度な技術を磨いてきた京都紋付。その技はやがて、綿や麻、ウールなどの天然繊維にも応用され、従来の洋装にはなかった圧倒的に深く、美しい「黒」を実現することに成功した。その鍵となったのが、研究に研究を重ねて編み出した独自の「深黒(しんくろ)加工」技術だ。

右が通常の染めのみ、左が「深黒加工」を施した生地。光を吸収し、ブラックホールのような絶対的な黒を表現する。

深黒加工によって生地はよりしなやかに、色落ちせず、驚くような撥水加工が施される。
「深黒加工」とは、布地の繊維の奥まで薬品を沁み込ませ、さらに光の反射を抑える特別な技術を施すことで、まるで光を吸い込むブラックホールのような漆黒の表現を可能にした。単なる「黒」ではなく、深さと品格をたたえた「深黒」。京都紋付が極めたこの技術は、アパレルの世界にかつてない「世界で最も黒い黒」をもたらし、国内外のブランドから染めの依頼が舞い込んだ。

京都紋付の黒に染まる、国内外の様々なアパレルブランドとのコラボレーションが展開。
-


さらに荒川氏は、長年蓄積した染めの技術を活かし、ジャケットやワンピース、Tシャツに至るまで、さまざまな衣類を黒く“染め直す”サービスKUROZOME REWEARプロジェクト「K」を開始。たとえシミがついても、色褪せても、思い出のある服が“黒の魔法”にかけられたかのように新たな魅力をまとい、日常に再び戻ってくるのだ。

安全性と環境に配慮し、和装業界で唯一、国際的に安全を担保するエコテックスクラス1の基準に準拠する染料を使用する。

染料の準備が整った後に、染め替えする服を専用機械の中へ。

約2時間後、染め終えた服を機械から取り出し一度干す。完全に乾かした後、さらに深黒加工を施す。天然素材以外の糸は黒く染まらないため、ステッチが強調されるなど、思いがけない表情が生まれるのも染め替えの楽しみ。
今や全国から毎日のように依頼が届く染め替えサービスを開始したのは2003年。2015年に国連でSDGsが採択された以前のことだ。その先見性に驚かされるが、不要になった衣類を黒く染め直して再び着るというアップサイクルな発想は、モノを大切にする日本人の精神にも通じる価値観だともいえる。
ファストファッションが大量に廃棄される時代にあって、今日、環境への配慮という観点からも一層共感が高まるKUROZOME REWEAR。この仕組みはアパレル企業、百貨店などとも連携して拡がり、衣類廃棄物の削減にも寄与している。

さらに注目が集まっているのは、昨今取り組んでいる新しいサーキュラーデザイン(循環型デザイン)だ。天然素材以外は黒く染まらない特性を生かして、黒染め前と後とでデザインが変わることをはじめから意図したもので、1着の服を2度楽しめる利点がある。今後このサーキュラーデザインも、広く展開されていくことが期待されている。

語る言葉一つひとつに、伝統の技術を守る信念と熱意がこもる荒川氏。海外展開も視野に入れているという。
「伝統を守るとは、かたくなに古い型を守り続けることではありません。時代の声を聞きながら、受け継がれてきた技術と精神を、新たな形で生かしていくこと。それこそが京都紋付の考える『継承』のかたちです」
深く、強く、静かに語りかける黒。その黒をまとうことは、単に衣服を着るという行為を超えて、日本の文化と職人たちの魂を身にまとうようなもの。京都紋付の黒染めには、そんな誇りと美意識が確実に宿る。
最後に、これまでの成功の秘訣を語ってくれた荒川氏。
「結局、どんな挑戦にも必要なのは“決断”と“行動”、そして“継続”ですよ」その真っすぐな信念こそ、黒という色に込められた覚悟と通じ合っているようだった。

-