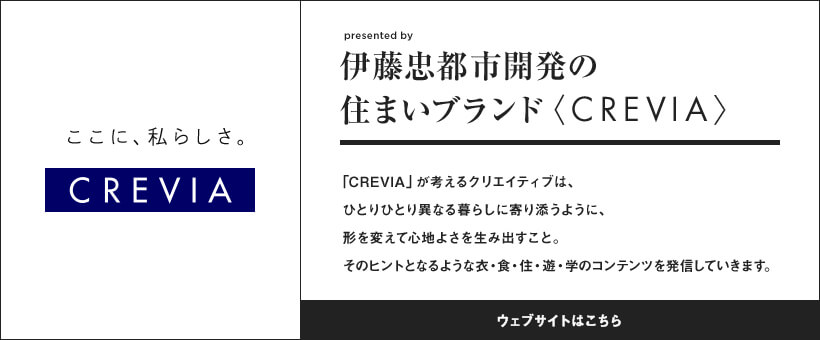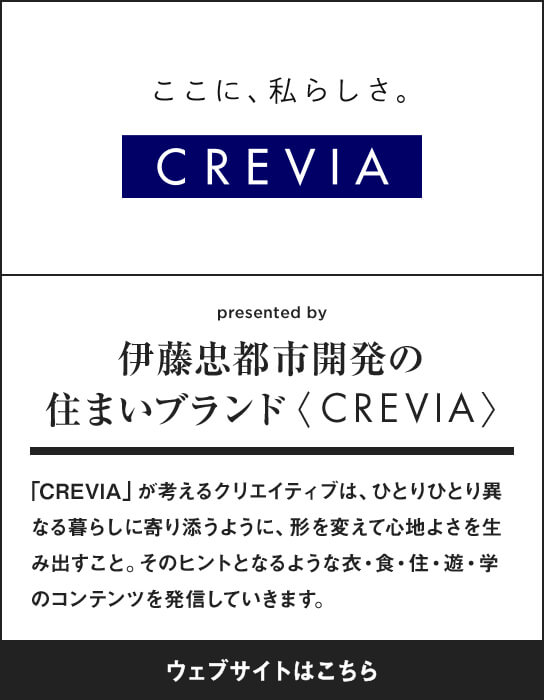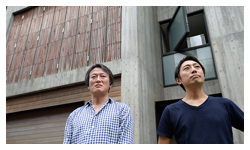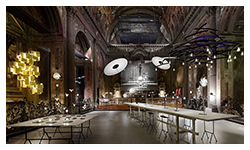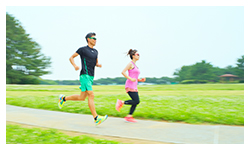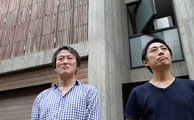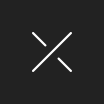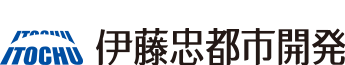富山・砺波平野に広がる日本最大級の散居村。ここには、人と自然が共につくりあげる精神風土「土徳」が静かに息づいている。今回訪れた「楽土庵」は、そんな土地の文化や暮らしの姿を未来へつなぐために生まれた、1日3組限定の宿。伝統的な家屋に流れる静謐な時間、郷土の恵みを受け継ぐ食や工芸、そして利他の精神に根ざした人々の営み──すべてが、自然と共生する豊かさを教えてくれる。訪れることで風景を守り、地域を再生するリジェネラティブ・ツーリズム。その本質に触れようと、金子麻貴さんと共に雪に包まれた楽土庵を訪ねた。


大人カジュアルを提案するファッションブランド「regleam」のディレクターを務め、9歳(2025年3月現在)の男の子のママとしてのライフスタイルも支持を集める人気インフルエンサー
Instagram:@mtmmaki

-


富山の砺波平野に雪が舞う中、静謐な大地に抱かれるようにして「楽土庵」にたどり着く。遠く立山連峰を望み、田園の中に家々が点在する美しい地。悠久の時を超えて受け継がれてきた風景が、今もなお穏やかに息づく散居村の一角に、この土地の風土を伝える「楽土庵」がひっそりと佇む。

築200年の伝統的な家屋、アズマダチを再生した宿は、白く染まる景色の中に溶け込み、この地に息づく「土徳」の象徴のよう。見上げれば、切妻屋根が降り積もる雪に覆われ、漆喰の白壁が冬の光を柔らかく受けとめている。

土徳とは、この土地に根付く精神のようなもの。民藝運動の主唱者であり、思想家でもあった柳宗悦が見出した造語で、積み重ねられてきた時の記憶、祈り、自然との共生によって育まれてきた目には見えない土地の品格が、ここ、楽土庵にも静かに宿る。

景色が映り込むガラスの扉を開けると、立派な梁が組まれた吹き抜けのラウンジが広がり、民藝運動の中心を担った一人、芹沢銈介の作品に静かに迎えられる。淡い灯りのゆらぎ、無垢の木から伝わる温もり、この宿を形づくる精緻な手仕事が醸し出す穏やかな空間。世界各地の民藝に加えて北欧の家具などがさりげなく置かれ、すべてが調和する中に流れる静謐な時間が、旅人の心をほどいていく。

到着後、ラウンジに設けられた立礼卓で供された、一服の抹茶と茶菓子。地元でつくられた干し柿と砂糖菓子には、今朝、雪積もる庭に咲いていたというローズマリーの花がそっと添えられていた。「毎日、茶菓子に添える草花を庭で摘んでは、自然界の生命に感動してしまうんです」と、この日もてなしてくれた宿のスタッフ、小久保さんが言葉を紡ぐ。目の前で丁寧に点ててくださった抹茶を口に含んだ金子さんが「美味しい」と声を漏らすと、「そのお茶は、私がおつくりしたのではないのですよ」という。「お茶碗やお抹茶、お湯の声を聞きながら、自ずと導かれて点てたにすぎません」。

こうした言葉は、この土地で暮らす人々が大切にする「おかげさまの心」から語られるもの。「すべては他力のおかげなんです」と、小久保さんが微笑む。
富山の人々の暮らしには、浄土真宗の信仰が深く根ざす。この散居村でも、人々は見えない力に導かれて生きてきた。他力によって支えられていることへの気づきと、感謝の心。長い時を経て育まれてきたこの地の信仰と共生の心が、この一椀にも込められている。
「かの板画家、棟方志功は、この地を訪れたことで『自我のちっぽけさに気づいた』そうです。以来、彼の作風はガラリと変わり、木の声を聞き、大いなる力によって生まれる作品を制作するようになりました」。
そう語る小久保さんの背後の壁には、棟方志功の版画がかけられていた。

加賀藩の奨励で富山県にも広まった茶の湯。今日の富山の茶道人口割合は国内2位を誇り、日常的に親しまれているという。会話を楽しみながらゆっくりとお茶をいただくもてなしに心癒された後は、宿が提案するアクティビティの一つ、書道体験のために寺へと向かう。雪降る中、人が互いに支え合う姿を模しているという木造の入り口で、住職が柔和な微笑みを湛えて出迎えてくださった。

書道体験は静けさに満ちた御堂で、まずは筆づかいを学ぶ。ひと筆ひと筆に集中することで、心が無になる時間。ひと通り学び終えると、最後に選んだ文字を書く。金子さんは“再び輝く”ことを意味する自身のブランド名regleamにちなんで、「輝」の文字をしたためた。
その後、住職に浄土真宗の教えを乞い、合掌の意味を知る。「手を合わせることで、相手を尊重する心が生まれます。そこに上下の関係はありません。人は皆、それぞれの役割を全うしながら支え合っているのです」。

帰り道、降りしきっていた雪がやんでいた。雲間からの陽光に山々の雪肌が煌めく中、金子さんが目を輝かせていう。「私自身、本当に日々、家族や社員に支えられていて。私の会社が成り立っているのも、一人ひとりの社員のおかげなんです。お茶を点ててくださった小久保さんや、ご住職のお言葉のひとつひとつが、とても心に響きました」。
-


日本でも類い稀な原風景が残る散居村。ここでは、自然と人、信仰と暮らしがゆるやかにつながり、循環している。宿に戻ると、楽土庵をプロデュースする「水と匠」の林口砂里さんから、この土地に宿る精神「土徳」についてさらに話を聞いた。

「散居村の美しい景観は、人々が自然と共生しながら自ずと生まれたものです。植生した屋敷林(カイニョ)は、厳しい風雪を防ぐだけでなく、木材や燃料など日々の暮らしを支える資源でもありました。水田の中に家があるのは、水はけのよいこの土地の水管理をしやすくするためです。そうして自然の循環に添った暮らしが営まれ、長い時間をかけてこの地域特有の美しい景観が形づくられてきました。誰かがルールを決めたのでもなく、散居村では、自然の摂理に寄り添うことで調和が生まれてきたのです」。

「作り手のはからいを超えたところに、 自然やおおいな るものからのはたらきが宿るーー柳宗悦が提唱した民藝 思想の根幹です。そのような”他力美”が宿るものをこの宿には設えています」。

客室にも、そんな土地の息遣いが満ちている。自然の恵みから生まれた素材によって、異なる表情が美しい3室。「土 do」では、左官職人が仕上げた土壁に、敷地の土を採取して制作した林友子のアートが寄り添い、すべてを受け入れる大地の安らぎが漂う。「絹 ken」では、富山の伝統である“しけ絹”がまろやかな光を湛えて、室内を繭のような優しさで包み込む。

「紙 shi」では、和紙職人・ハタノワタルの手漉き和紙が壁と天井一面にあしらわれ、柔らかな風情を醸し出す。どの部屋も、それぞれの素材の本質が、宿泊者の心を穏やかに解きほぐす。さらになぐり床や、網代天井などの精緻な職人技も、部屋に品格を添えていた。

各部屋には濱田庄司や河井寛次郎をはじめとする数々の民藝の品々が展示され、家具にはハンス・J・ウェグナーのソファや、オーレ・ヴァンシャーの椅子、ルイス・ポールセンのランプやバルーチ族のラグ、李朝の骨董など、数え切れないほどの名品が配されている。
美しいものと過ごす時間は暮らしを豊かにする。つくり手と使い手、運び手の三者が関わることで美が広がるという民藝の思想に基づき、宿にしつらえられた民藝や工芸品の多くは購入できるという。まるでギャラリーを訪れたかのような趣だ。
宿にあしらわれている数々の調度品もまた、その精神から生じる空気感を纏う。民藝のみならず、唐や李朝の骨董、中東の織物、さらに現代アートや北欧の家具など、時空も国境を超えてすべてが違和感なく溶け合うのは、いづれも人と自然が共に創り上げた「無心の美」を宿しているからだ。
夕暮れ時、雪に覆われた田園は淡い藤色に染まり、静寂がいっそう深まる。遠くの山々は霞み、冷たく澄んだ空気が頬をかすめるのを感じながら、併設されたレストラン「イル クリマ」へ。

ここでは富山湾の新鮮な魚介や、郷土料理の知恵を生かしたイタリア料理が供される。土地の恵みを感じながら、温かみのある器、素材を活かした料理に五感が満たされた晩。この日腕を振るっていたのは22歳のシェフ、樋口文也氏で、若き才能に託す宿の粋な想いが伝わってきた。
-


朝目覚めると、雪はさらに降り積もり、窓の外は一面の銀世界。幻想的な雪景色を眺めながら、丁寧に用意された朝食の温もりと、宿の人々のさりげない気遣いに心身が潤う。

朝食後は、チェックアウトまでの時間、アートや民藝、仏教思想などにまつわる本が多数並ぶライブラリーの書棚から心惹かれる数冊を選び、ゆっくりと手に取りページをめくる。ラウンジに隣接するライブラリーは、内藤礼の小さな木彫りと絵画が展示され、この宿の小さな聖空間のようだった。

旅の終わりが近づき、雪の清らかさと呼応する金京徳の白磁を見つめていた金子さんに、今回の滞在の感想を聞く。
「ここは、すべてが澄んだ空気を纏い、優しさが宿る場所でした。『他力』に感謝するおかげさまの心と、自然と共に生きる人々の思いやりが隅々にまで感じられて。エゴからではなく、風の音を聞き、空気を読み、自然と共に生きることで創り上げられたという景観も美しく、雪景色にはんなりとした情緒が感じられるのも、この土地の土徳なのかもしれません。空の表情や光も刻々と変わり、ずっと眺めていたくなります。五感が研ぎ澄まされ、目まぐるしい都会の生活の中で置き忘れてしまった何かが蘇ってくるような感覚は、まさに再生につながるようでした」。
しかし、この稀有な美しさを宿す散居村も、今の姿を失いつつあるという。楽土庵では、宿泊費の2%を散居村の保全基金に充て、富山の土徳を未来へつなげることを目指す。旅人と地域がともに再生していく――そんな「リジェネラティブ・ツーリズム」の提案だ。
剪定した屋敷林の枝を再利用し、抽出したアロマ精油をアメニティや製品に生かしているのも、屋敷林を維持し循環させるため。

「私自身、今回、これまでにない旅のあり方を心の奥深くに感じることができました。散居村の美しい風景と『土徳』を伝え残していくために、その土地を知り、想い、訪れる。それだけでも再生のための支援につながるのですね。次は水田に水が張る季節に、家族と訪れてみたいです」。

-

人気の記事ランキング
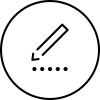 LEARN
LEARN
-
![金子 麻貴]()
REGENERATIVE TOURISMリジェネラティブ・ツーリズムの本質を求めて
-
![大河内 康晴|Shimon Hoshino]()
「サウンドクチュール」に学ぶ心地よい音と香りの見つけ方
-
![岩瀬 功樹]()
DIGITAL TRANSFORMATIONIoT・AIがもたらす新たな豊かさとは?
梓設計、AI・IoT導入リーダー岩瀬功樹氏に聞く
-
![加藤 佑]()
SUSTAINABLE LIFE「住まい」から考えるサステナビリティ
サステナブルな生活をスマートに始めよう
-
![大野重和]()
デザイン先進国オランダドローグデザインのいま
レフトハンズ大野重和が、アイントホーフェンを訪ねる
-
![チームデジマ]()
新たな可能性を生み出す場所「Innovation Space DEJIMA」
チームデジマが語る「DEJIMA」という場所
-
![生方 ななえ]()
「AZERAI」に学ぶ“おもてなしの美学”
生方ななえが探る「AZERAI CAN THO」〈後編〉
-
![生方 ななえ]()
「AZERAI」に学ぶ新たなデスティネーション
生方ななえが探る「AZERAI CAN THO」〈前編〉
-
![手塚 貴晴]()
クリエーティブな環境が子どもの心と体を育てる。
建築家・手塚貴晴が「世界一楽しい」幼稚園を語る。
-
![来生 ゆき]()
世界にひとつだけの空間をDIYで、自分でつくる!
TOOLBOX・来生ゆきさんに学ぶ壁を使った簡単DIY
-
![伊藤立平]()
住む人の想像力を刺激する 「間取りのない家」へようこそ
テリー伊藤さん・建築家伊藤立平さんと考える未来のマンションのかたち
-
![各務亮]()
職人技をリビルドして京都はデザインの最先端になっています
100年後にも続いていく手仕事を作る
-
![鄭秀和]()
デザインは「出汁を引く」のと同じ感覚です
インテンショナリーズの引き算建築哲学
-
![日比野 好恵]()
「いいデザイン」の裏には、デザイン心理学がありました
iPhoneからキッチンまで、使いやすいアイテムは人間中心に出来ている
-
![菅未里]()
“未来の文房具”をテイスティングする
文房具ソムリエール菅未里さんも夢中になった!?
-
![田代 かおる]()
モノを空間と場所から見た、もう一つの「ミラノ・デザインウィーク」
ミラノ在住のライター田代かおるがリポートする、世界最大のインテリアの祭典
-
![田中 達也|中村 ダヨネ]()
リユース・リサイクルの究極を徳島・上勝町RISE&WINに見る
建築家・中村拓志氏のサステナブル建築案内 Vol.2
-
![中村 拓志]()
高知・梼原町を魅せる隈研吾建築
建築家・中村拓志氏のサステナブル建築案内 Vol.1
-
![遠山 正道]()
「モノ」にまつわるストーリーを受け継ぐライフスタイル
遠山正道氏が考える「モノ」の価値
-
![伊藤 徹也]()
プロに学ぶスマートフォン撮影術
SNSでカッコいい写真をアップするためのガイド
-
![木村 貴史]()
Plantica木村貴史が提案する贈る花・迎える花
飾る場所・喜ぶ相手で考える選び方・楽しみ方
-
![安田 美沙子]()
安田美沙子の京都のくらしデザイン探訪
「むかし」と「いま」のスタイルを学ぶ
-
![淵上 正幸]()
淵上正幸と巡る話題の海外集合住宅建築
建築ジャーナリスト・淵上正幸と世界のセンセーショナルな集合住宅を探る
-
![片山 正通]()
「ワンダーウォール」に学ぶアートのある住まい
インテリアデザイナー片山正通氏の事務所「ワンダーウォール」からアートと暮らすヒントを見つける!